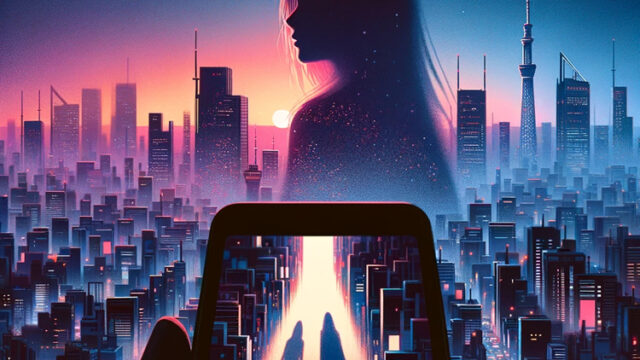都内のいたる場所で太一と真理は情熱的な時を過ごした。太一の部屋での初めての夜から、彼らの関係は加速度的に進展していた。パーキングエリアの隅、居酒屋の個室での隠れたスリル、さらには夜景のきれいな高層ビルの展望台でも。まるで2人の情熱は止めどなく、その度に新しい場所、新しいシチュエーションを探求していた。
しかし、その激しい情熱の中で、太一は真理の言動から少しずつ違和感を感じ始めるようになっていた。2人は頻繁にデートを重ね、その中で太一は真理の会社や上司、特に部長についての話をよく聞いていた。真理は仕事に打ち込む姿勢を持ち、特に部長との仕事が増えるにつれ、彼女の話題に部長の名前が多く登場するようになった。
初めは太一はそれに対して特に気に留めていなかったが、ある日、彼女のスマホが鳴った際に、画面に映る部長からのメッセージに目を留めてしまった。真理はそれを速やかに非表示にしたが、太一はその後、部長との関係に疑問を抱くようになった。
「真理、最近部長との仕事が増えてるって言ってたよね?」太一はある日のデート中、真面目な顔で問いかけた。真理は少し動揺した様子で、目を伏せ、「うん、プロジェクトがあって、一緒になることが増えたの。」と答えた。
しかし、真理の回答は太一の心の中の疑問を払拭するには至らなかった。真理が仕事で遅くなる日が増える中、太一の心には不安が募っていった。真理との情熱的な時間は以前と変わらず続いていたが、彼の胸中には次第に疑念の影が潜むようになった。
ある晩、真理が太一の部屋に訪れた際、太一は彼女に向かって直球で尋ねた。「真理、君と部長との関係は、本当にただの上司と部下なの?」
真理は深呼吸をし、しっかりと太一の目を見て言った。「太一、私はあなたのことが大好き。部長はただの上司よ。本当に。」
太一は真理の言葉を信じたいと思いながらも、何かを感じ取ってしまった違和感は容易には消え去ることはなかった。そして、二人の関係にはわずかながらも亀裂が入り始めていた。